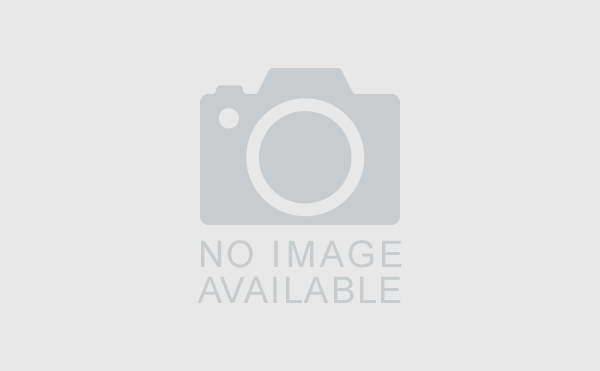避難所運営研修を実施 平岡地区町内会連合会 各町内会防災防犯部長ら30名参加
平岡地区町内会連合会は8月22日(月)、平岡中学校で避難所運営研修を実施しました。各町内会の防犯防災部長ら約30人が参加し、災害発生時の避難所の運営について学びました。

各町内会の防犯防災部長らが参加した避難所運営研修会=平岡中体育館
はじめに中川昇町連会長が「コロナで2年間、町連活動が思うようにできませんでしたが、ようやく防災研修を実施できるようになりました。しっかり学んでいざというときに備えましょう」と挨拶しました。

平岡中の備蓄庫で防災物資を確認する研修参加者
研修は、はじめに札幌市の担当職員から、避難所の開設や運営について学びました。
2018年の北海道胆振東部地震の際の避難所運営は、市職員主体で行い、地域住民(避難者)主体の運営は行われませんでしたが、より大規模な災害が発生し、避難所運営が長期化する場合は、地域住民(避難者)主体の運営が検討されます。原則として発災日から4日目以降は地域住民主体の運営になります。
したがって、地域にとって、避難所運営について日ごろから学んでおくことが大事です。
避難所は、活動グループを総務、名簿、情報、食料・物資、施設管理、救護、衛生、ボランティア統括などに分け、運営します。
避難所では、入退所、外出・外泊等の管理、要配慮者・負傷者への対応、備蓄物資の搬入・配布、食料の配給、避難者への情報提供、区災害対策本部への連絡等の様々な仕事があります。

給水設備の話を聴く
研修では次に、防災行政無線の使い方を勉強したり、校内の備蓄室を見学し、毛布や寝袋、ストーブなどの防災物資が備えられていることを確認したりしました。
最後に、図上で避難所運営ゲームを行い、避難所運営を疑似体験しました。
平岡地区町連では、今回の研修のほかに、平岡中央中(8月2日)、平岡中央小(8月17日)、平岡小(8月18日)、平岡南小(8月19日)、清田区体育館(9月12日)でも、町内会副会長らを対象に避難所施設見学会を実施しています。